フランス人権宣言
今日(2024/03/14)クラシックTV と言う番組でフランス革命とベートーベンが取り上げられていました。
番組を見ながら一般常識の琴線に触れたので以下の過去問を取り上げます。
「フランス人権宣言」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 個人の権利としての人権を否定して、フランスの第三身分の階級的な権利を宣言
したものである。
2 人権の不知、忘却または蔑視が、公共の不幸と政府の腐敗の原因に他ならない、
とされている。
3 人は生まれながらに不平等ではあるが、教育をすることによって人としての権利
を得る、とされている。
4 あらゆる主権の源泉は、神や国王あるいは国民ではなく、本質的に領土に由来す
る、とされている。
5 権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されないすべての社会は公の武力を
持ってはならない、とされている。
フランス人権宣言とは
フランス人権宣言は フランス革命を国民議会で採択宣言されました。1789年の事でした。
内容をザックリと要約すると
自由と平等の原則
人民主権
言論の自由
三権分立
所有権の保障
辺りが主な内容です。
現代の法律に通じる原則がここにあります。世界中の国に影響したと言ってもいいかもしれません。
問題の解答
肢1は誤りですね。階級的な権利ではなく個人の権利をうたっています。
肢3も誤りっぽいですね。生まれながらに不平等であるの部分が妥当ではなさそうです。日本国憲法の第26条から想像すると、せいぜい許されるのは能力に応じて区別する事までではないかと予想できます。→わからなくても生まれながらに不平等であるなんてのは状況でそうなってしまうならまだしも端からそれをうたうのはどうなんだ?と誤りと感じます。
肢4も誤りですね。主権は人民にありです。
悩むのは肢2と5ですね。
肢5は妥当ではないのですが理由は、
16条で「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。」→三権分立の事を述べている
また12条で「人および市民の権利の保障は、公の武力を必要とする。この武力は、すべての者の利益のために設けられるのであり、それが委託される者の特定の利益のために設けられるのではない。」とあり妥当ではないです。→武力保持の容認と不当な行使の禁止
正解は肢2となります。
興味ある方は短いので検索して全文見ることをお勧めします。憲法を超要約したと言ってもいいくらい簡潔で分かりやすい宣言です。
管理人の脱線コメント
ここでジャジャジャジャ――ーーン ベートーベン先生登場です。
フランス革命当時ベートーベンはボン(ドイツ)にいたようです。当時、ヨーロッパ中の音楽家は交流を繰り返していたようです。その中でフランス革命後のフランスの平等自由、主権人民と言う風も感じたことでしょう。
1792年ハイドンの弟子となるべくウィーンを訪れます。
文化の中心はパリやウィーンだったんでしょうね。
当時のウィーンはフランス革命のあおりで報道の自由が規制されていたようです。
交響曲第9番は40歳頃の作品だそうです。大体1810年ごろです。
作詞は詩人のシラーと言う人物。
ベートーベンはこのシラーの詩を愛読していたようです。多少のアレンジは加えたようですが第9が発表されました。
様々なサイトで日本語訳が掲載されているので割愛しますが、
歌詞の訳の中に 平等博愛自由への渇望の様な物が感じられます。
長く続いた階級社会の中で音楽家としてそれを利用しなければならない事もあったでしょう。しかしながらフランス革命の風を感じなにかもやもやとした渇きのようなものもあったのではないかと思います。改めて歌詞を見るとそんなことが感じられました。
年末によくやってる第9の中に憲法の精神のもとになった宣言へのあこがれが入っているなんて一気に身近に感じませんか?
これでもう人権宣言1789って覚えちゃいますね。
さらに 平等、主権は国民にあり、内容もザックリ頭に入っちゃいます。
この辺りに興味のアンカーが打たれていれば、基礎法学などで大陸法やいろんなことが出てきても、それが足場になり攻略ルートも見えるかもしれません。
試験では法律的な考えが出来るかが問われます。
普段から興味を持って法律的な方面から見たらどうなんだ?と考え、ルートは遠いけど、ここと繋がってそうだなと感じる事は大きな力になるのではないかと思っています。
なんてTV 見ながらでも一般常識のネタはどこにでもあり、即検索の興味本位で掘り下げましょう。と言うお話でした。
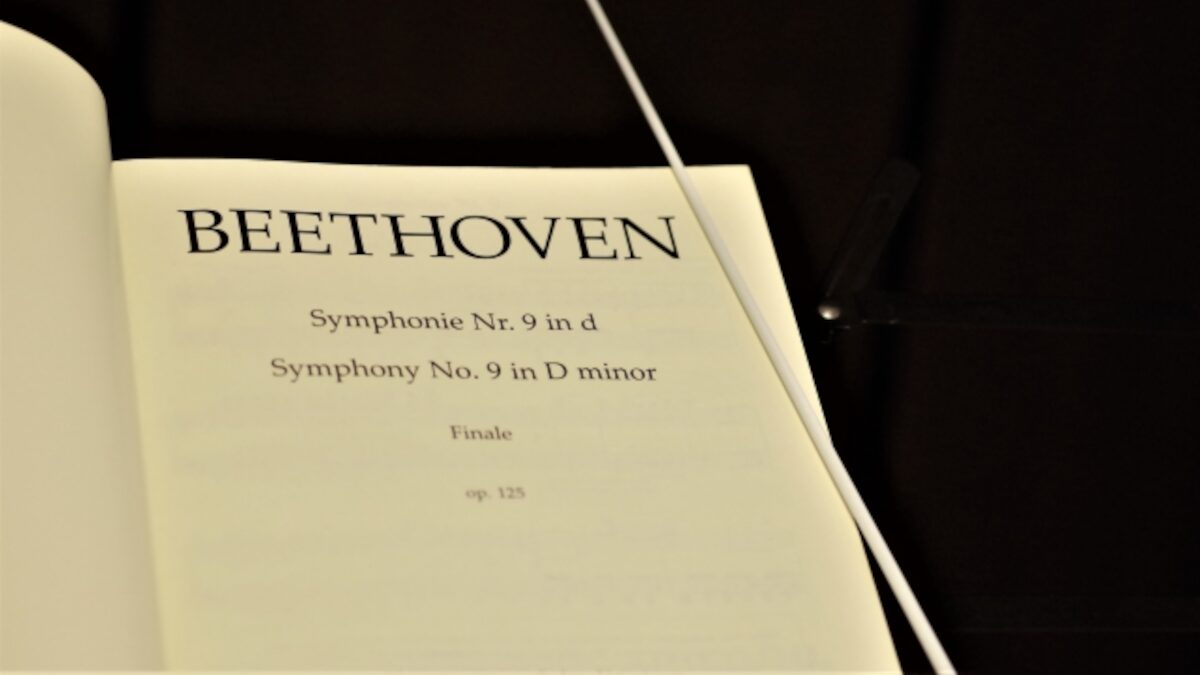


コメント