意思能力からさらに踏み込む行為能力です。判断能力の程度により規定を設けています。
4条は成年年齢について、5~6条はその年齢に達していない未成年の法律行為についてです。
民法 第4条
条文
(成年)
第4条 年齢十八歳をもって、成年とする。
引用:民法
解説
4条 年齢十八歳をもって、成年とする。
民法 第5条
条文
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
引用:民法
解説
5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
民法 第6条
条文
(未成年者の営業の許可)
第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
引用:民法
解説
第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
関連条項集
民法 第120条
5条2項では1項に反する行為は取消しできるとしています。
ではだれが取り消すのか?と言うのが120条に定められています。
条文
(取消権者)
第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
引用:民法
解説
民法第122条、126条
じゃあ反対に取り消せないときはどんな時?って思いますよね。ぜひ5条の隣においてください。
後から出てきますが以下です。
122~126条にかけて記載があります。
条文
(取り消すことができる行為の追認)
第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
(法定追認)
第126条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
引用:民法
解説
120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
親族編
民法 第712条
重要表現:自己の行為の責任を弁識するに足りる知能
(責任能力)
第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
引用:民法
概ね12~13歳程度であるとされています。13歳程度であれば自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えているとされています。
ほかに713条、714条にその際の責任はどこに?と言ったことに関する条文があります。
債権(不法行為の範囲)にある事ですので、ここでは責任を負わない年齢が有りますという事(自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき という文言は重要です。)と、その際の責任の所在と監督責任についての条文があると含んでおけばいいと思います。
民法 第780条
身分行為は単独でできます。
(認知能力)
第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
引用:民法
認知は後見人の同意は不要
民法 第838条
親族編に未成年者に対する規定が多数あり、ここと横断するように問題が出される可能性があります。
5条に関連する規定が親族編に在る事だけでも記憶にとどめておいてください。それだけで練習問解く際にわからなくても、どのあたりを調べれば良いか分かりますからイライラしないで済みます。
(後見の開始)
第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2 後見開始の審判があったとき。
引用:民法
問題で 未成年者に対して親権を行う者がないときにのみ貢献が開始するなんて問題が出たら×になりますね。
他にも
839条(未成年後見人の指定)
840条(未成年後見人の選任)
841条(父母による未成年後見人の選任の請求)
など規定があります。
民法 第961条
遺贈と死因贈与は似ているようで違います。
遺贈は単独行為:死因贈与は法律行為(契約で代理人の同意が必要です)
(遺言能力)
第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
引用:民法
遺言は意思表示を要素とする単独行為
15歳以上で遺言によって遺贈可能
注意点:死因贈与の場合、契約であるため 死因贈与を行うには成年であることが必要です。
管理人コメント
このようにたった1行2行の条文にかなりの条文がその後に付随してきます。これらが同じ問題に並ぶと混乱したり原則からそれて考えてしまうようになります。
総則は大変ですが隣に置いておきたい条文がたくさんあるので、ぜひ関連付けて学習するといいと思います。
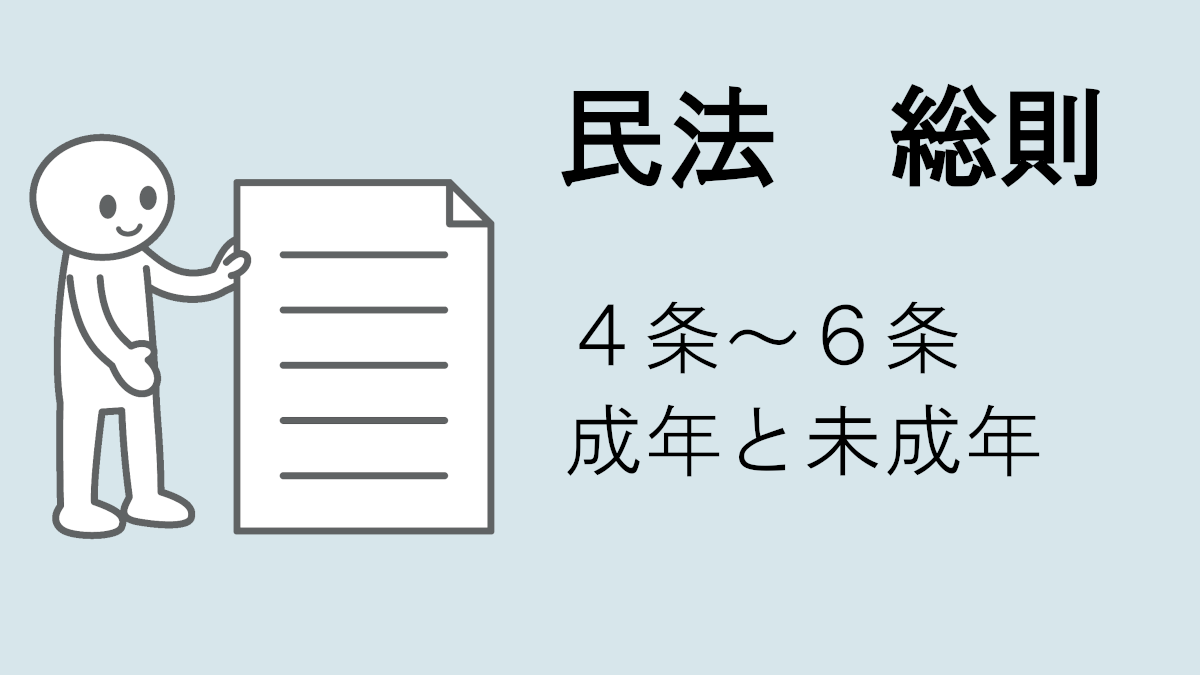


コメント