民法15~18条
制限行為能力者の中では制限が軽いのが被補助人です。本人の権利義務がある程度高くみとめられています。
民法 15条
条文
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
引用:民法
解説
15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第17条1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
民法 16条
条文
(被補助人及び補助人)
第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
引用:民法
解説
明確です。やはり自称では効果が発生しません。
民法 17条
条文
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
引用:民法
解説
17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
民法 18条
条文
(補助開始の審判等の取消し)
第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
引用:民法
解説
18条 第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
→補助開始の審判の取消しについてです。
他の制限行為能力者の規定と同じです。理由がなくなったのに権利義務をそのままには出来ません。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
→審判した同意権も取り消すことが出来ます。
前条第1項=同意権の審判の事
3 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
→同意権と代理権を取り消すには補助開始の審判も取り消します。
前条第1項=同意権の審判の事
876条の9第1項=代理権付与の審判の事
関連する条項集
やはり親族編に関連する条項があります。
民法 876条の6~876条の10ですが重要な部分は以下です。
重要ポイント(親族編)
解説
前提として補助開始の審判に本人の同意が必要。
同意権については、第13条第1項に規定する行為の一部に限り付与の審判が出来る。その際、本人の同意が必要。
ここから代理権を追加したい場合が以下
①補助人に代理権を付与する審判が出来る→重要です。本来代理権はありません。法定代理人の地位はありません。
②代理権の審判は本人の同意が必要
③補助人の選任は家庭裁判所の職権→混同しがちですが選任が家庭裁判所でも代理権が当然に付与されてはいません。その為法定代理人の地位にありません
準用される事項
保佐人と同じように成年後見人の規定が多く準用されています。
876条6~876条の10には条項が多く並び非常に読み難いです。ですが試験対策上重要な部分は多くなく、当然に法定代理人ではない事もあって報酬や費用に関する規定を債権編の委任の分野から準用しています。
試験対策上の重要度は低いです。参考として見出しを書きだしたのが以下です。この辺りが準用される事項になります。
843条2項~4項:(成年後見人の選任)
844条:(後見人の辞任)
845条:(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
846条:(後見人の解任)
847条:(後見人の欠格事由)
644条:(受任者の注意義務)
654条:(委任の終了後の処分)
655条:(委任の終了の対抗要件)
843条4項:(成年後見人の選任)の利害県警の有無と一切の事情について
844条:(後見人の辞任)
846条:(後見人の解任)
847条:(後見人の欠格事由)
850条:(後見監督人の欠格事由)
851条:(後見監督人の職務)
859条の2:(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
859条の3:(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)→補助監督人が財産を処分するには裁判所の許可が必要。ココ大事なポイントではないかと思います。
861条2項:(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
862条:(後見人の報酬)
これ被保佐人と同じように準用されています。
644条:(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
859条の2:(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
859条の3:(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
861条2項:(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
862条:(後見人の報酬)
863条:(後見の事務の監督)
876条の5第1項:(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
654条:(委任の終了後の処分)
655条:(委任の終了の対抗要件)
870条:(後見の計算)
871条:後見の計算の立ち合い
873条:(返還金に対する利息の支払等)
832条:(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
管理人コメント
繰り返しになりますが、被補助人は 開始の審判、同意権付与の審判、代理権付与の審判に本人の同意が必要です。そこが大きなポイントになります。また保佐人がそうであったように補助人も当然に法定代理人ではありません。
そこを常に意識するようにしてください
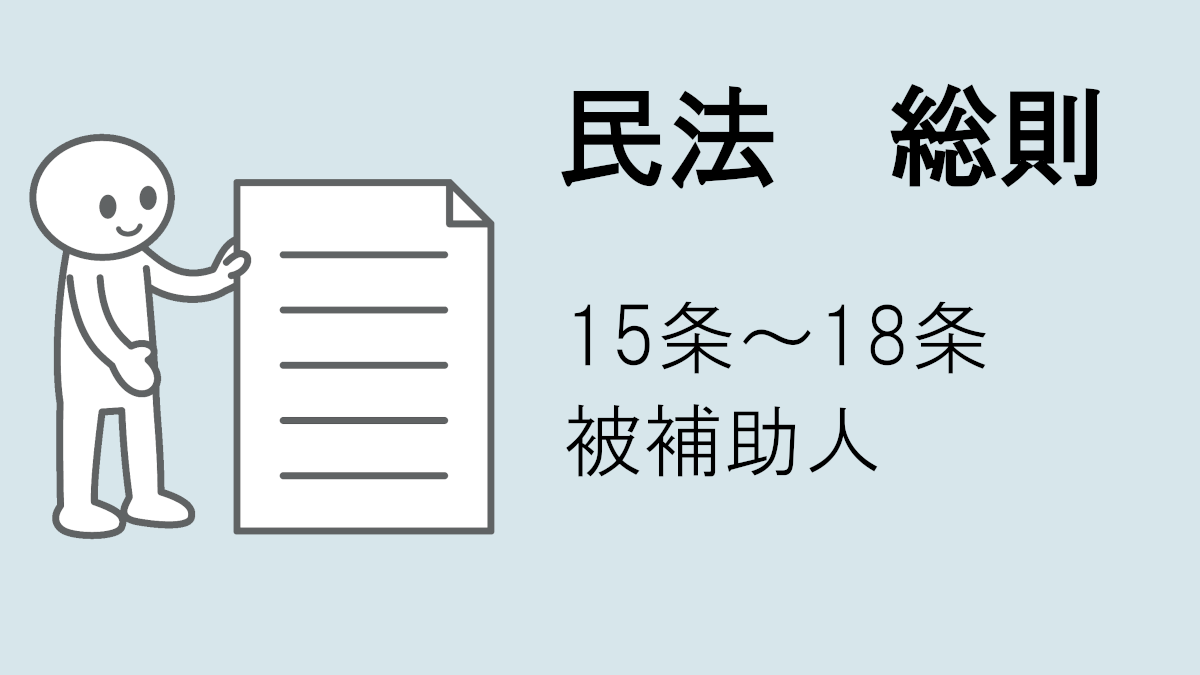


コメント