管理人のたどったルート
あなたは何を使いましたか?
管理人の私が試験勉強に使った教材はU-CANの行政書士講座です。
内容はやや薄い部分が有ると思いますがその為進みが速いです。脳内にサイトマップと棚を作るのに最適でした。
又出題頻度の高い条文や判例がところどころに配置してあり何度見返しても発見があるというものでした。
もっともU-CANしか知りませんので、他と比較はできません。
ただ合う合わないというのは有るはずですので自分に合った教材を見つけることは大事です。
繰り返し学習
1周目
通信講座で動画視聴メイン:何となくわかったように感じる1カ月半程度で一周して過去問にチャレンジしましたが惨敗20%程度しかできません。
脳内に残る情報が少なく愕然とする。
学習直後の○×問題はそれなりなんですが翌日にはもうあやふやになります。
しかし心配はしていませんでした。時間は1年ありましたし。(学習開始が11月)
2周目
動画視聴しながらテキストも読む。 一歩一歩基礎を固めようと思い少しでも疑問点があれば講座の質問機能で回数MAX毎日質問 過去問チャレンジしましたがやはり点数が上がりません。
民法分野の学習でこの質問機能を最大限使いましたが、細かいところに着目していても理解度は上がらない事を痛感
講座の講師さんたちにもかなり負担をかけたと思います。
合格した今思うとこの質問した経験が、文章理解や記述式に役立ったと思います。
わからない事を簡潔に他人に説明するなんてことは普段しませんからいい機会だったのではないかと思います。
通信講座受講される方はこの質問できるという事は大きなメリットになるかと思います。管理人にはそうでした。
3周目
理解度の上昇に効果的ではなかったため細かく質問するのはやめました。かわりに検索することを覚えました。
細かく質問するのをやめた理由を管理人コメントに書いています。

この時指導されたのは本当にラッキーでした。その節はお世話になりました。と言う気持ちです。
そしてこの辺から会社法、基礎法学はパスしました。
動画視聴とテキスト併用しながら手書きで要点をまとめるノートを作る。 少し点数が上向く。合格には程遠い状態
4周目
ノート作りをワードに変更
民法、行政法中心
憲法は読み込みに注力
少し点数が上向く 使用フォントで読みやすさが全く違う事に気が付きます。
5周目
ここでも民法、行政法中心
ワードでノートを作りながら、短い文章で標語の様にまとめる。
例:心裡留保は原則有効
抵当権は物権
など
途中から標語にしたものを声に出して音読
少し上向く
6周目
音読はやめ アウトプットに注力
やはり民法、行政法中心
この辺りから一般常識も過去問中心に実施
ひたすら過去問を回答しながらわからない部分のみテキストで確認。ノート作り一時停止して不明点は無理やり答えず素直にテキストを開くようにする。
テキスト巻末の索引が非常に役に立ちました。
ここまでで7月も終わりかけ。特に民法、基礎法学の点数が上がらずやや焦りがでる。
憲法は読み込みの効果が出始めたのか一部の難問を除いて上向く。管理人は 2重の基準論と合理性の基準がごっちゃになり理解に時間がかかりました。
7周目
8月に入り同じことを繰り返していても効果が上がらないのは見えているのであえて、苦手だと思っていたことをやってみる事にする。
民法を条文から事例を導き出したり、事例を条文に落とし込んだりしてみる。
これが管理人には合ってたようです。
学習終盤期
本業の仕事上9月10月に出張があり進まなくなると考えここよりスパートと思い力を入れました。
9月いっぱいまでテキスト一周する
8月からは、ほぼ全部の教科を一周しました。9月10月と本業の出張が2週間単位で続き、進みが悪くなり結構焦りました。
特に一般常識分野の総務省管轄部分と商法会社法はこれで最後と思い力を入れました。
10月は文章理解と法学の用語、試験に使われそうな漢字、記述式の練習
隙間時間に民法、行政法の問題をやりこむ。
この記述式の練習をしたことが、択一問題のいい見直しになったように思います。
11月は10日まで時間を計測しながら試験の練習
とやりました。
で試験当日となったわけです。
回答を転記して自己採点は、結果は変わらないと思いやりませんでした。当日は体調も良く緊張もせず出し切った感がありました。
自己採点していないので合否がはっきりしませんでした。
その為学習を回していました。
前半かなり時間を無駄にした感じがあります。


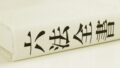
コメント