民法の根元1編1章1条です。
民法の大原則がここにあります。短い中にも憲法をなぞるような条文となっています。それだけ根幹に近いという事です。
民法 第1条
条文
(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
引用:民法
解説
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
管理人の主観
この条文により一番最初に民法は法律による留保が付けられていると思っていいでしょう。
民法からは遠い場所に位置しているが、憲法29条財産権が問題になった 「奈良ため池条例事件」があります。対して憲法12,13,22各条には公共の福祉と言う言葉が出てくる。個人の権利義務に関する事でも公共の福祉が重視されます。また権利の乱用についても言及があります。
この事から考えられるのは個々の人間の間を規律する民法であっても それは大きな公共の福祉の傘の下にあるという事がこの1条に表現されていると思っています。
基本的に一部を除き権力側を規律する法律である憲法ですが、その考え方は広範囲に影響しあっています。大きなくくりで権利行使する側を規律して相手方の権利を守る事が根底にあるのだと思います。
民法の各条文を読むときにその背後に薄っすらと憲法とこの民法1条の存在を感じることが大事です。
民法 第2条
条文
(解釈の基準)
第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
引用:民法
解説
第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
管理人の主観
これも全体に影響する条文です。
憲法第13条にこうあります。 「すべて国民は、個人として尊重される」
人権を最大限重視している事の現れでしょう。やはりバックボーンに憲法が隠れています。
また、第14条には 「すべて国民は、法の下に平等であつて」とある反面
第26条には 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とあります。
そして平等には絶対的な平等とそうではない平等があるということが予定されている事の現れです。
しばしばこの平等に関することが争いになります。
有名事件に
日産自動車女子若年定年制事件と言うものがあります。
これは憲法14条と民法90条が争いになった事件です。
憲法が直接私人間に適用されるかについては 各説があります。
直接適用、間接適用、無効力 などです。
公法関係が私法関係に影響を及ぼすかについてはこのように諸説ありますが、考え方の根底には憲法が隠れています。
この1~2条から直接出題される可能性は低いと思いますが、大事なのは各条文の後ろに民法1条や憲法の存在を薄っすらでも感じる事です。
著者のコメント
私法であっても公法の影響を受ける。
これが常識で判断すればいいんだろ?と思っていると躓く理由です。その常識は人の数だけある常識でありその為これだけの数の条文があり膨大な判例があるわけです。
このように民法分野ではなくてもお互いに影響しあって法律は組み立てられています。
総則部分は全体に影響する事を覚えておいてください。
日本の法律の総則はなんだ?と考えたらそれは憲法ではないかと思っています。
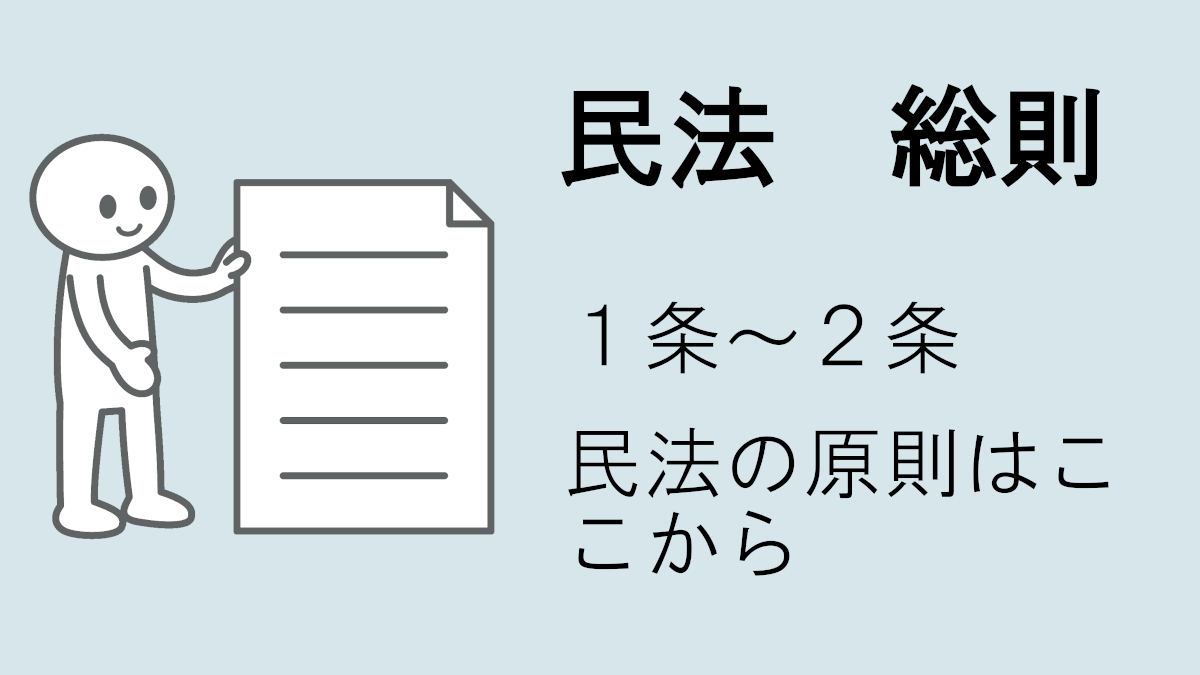


コメント